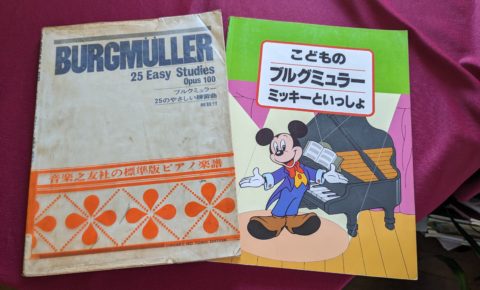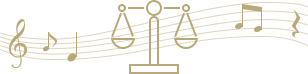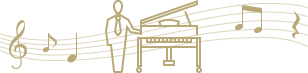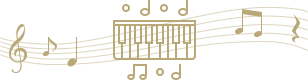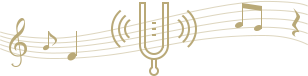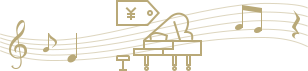7歳からピアノ。13歳から打楽器。他にもテナーサックスや沖縄三線、合唱に挑戦し幅広く取り組む。現在は飲食店での接客調理、WEBライターや打楽器指導を行っている。 尚美ミュージックカレッジ専門学校打楽器専攻卒業。大阪芸術大学通信教育部音楽学科卒業。中学校・高等学校教諭一種免許(音楽)取得。
目次
- 〈簡単に解説〉交響曲とはどんな音楽?
- 交響曲の定義
- 交響曲の起源、生みの親は?
- 交響曲の作品番号の意味は?
- 〜交響曲の歴史をさかのぼろう〜交響曲ができるまで
- ルネサンス期(紀元前14~17世紀)
- バロック期(17~18世紀初頭)
- 古典派期(18~19世紀初頭)
- 交響曲の特徴5つ
- 特徴① 多くの楽器が使われる
- 特徴② 複数の楽章で構成されている
- 特徴③ ソナタ形式の使用
- 特徴④ さまざまな感情を表現している
- 特徴⑤ 主題の変奏や対比
- 交響曲と協奏曲の違いは?
- 有名な作曲家と交響曲をご紹介◎
- ハイドン
- 交響曲第94番ニ長調「驚愕」
- 交響曲第45番ヘ短調「告別」
- モーツァルト
- 交響曲第40番ヘ短調
- 交響曲第41番ハ長調「ジュピター」
- ベートーヴェン
- 交響曲第5番ハ短調「運命」
- 交響曲第9番ニ短調「合唱」
- ドヴォルザーク
- 交響曲第9番ホ短調Op.95「新世界より」
- 交響曲第7番ニ短調Op.70
- チャイコフスキー
- 交響曲第4番ヘ短調Op.36
- 交響曲第6番ヘ短調Op.74「悲愴」
- まとめ
「交響曲ってなに?」
「交響曲と協奏曲の違いは?」
クラシック音楽に興味をもったものの、交響曲が何かわからない人が多いのではないでしょうか。
この記事では音大卒業の経験をもつ筆者が、交響曲について解説します。
- 〈簡単に解説〉交響曲とはどんな音楽?
- 〜交響曲の歴史をさかのぼろう〜交響曲ができるまで
- 交響曲の特徴5つ
- 交響曲と協奏曲の違いは?
- 有名な交響曲と作曲家をご紹介◎
交響曲の構造や要素について知ると、作曲家や時代背景の理解が深まり、音楽鑑賞がより楽しめるようになるでしょう。
〈簡単に解説〉交響曲とはどんな音楽?

交響曲とは複数の楽章からなる大規模な作品で、管弦楽団(オーケストラ)によって演奏される楽曲ジャンルです。
ここでは以下3つについて解説します。
- 交響曲の定義
- 交響曲の起源
- 交響曲の作品番号の意味
交響曲の概要を知ると、交響曲とは何か理解したうえで音楽を楽しめるようになります。
交響曲の定義
交響曲の定義は「管弦楽のためのソナタ形式による楽曲」(引用:デジタル大辞泉)です。
各国での呼び方は以下のとおりです。
英語:symphony(シンフォニー)
ドイツ語:sinfonie(シンフォニー)
イタリア語:sinfonia(シンフォニア)
交響曲の起源、生みの親は?
交響曲の起源は18世紀後半といわれています。
18世紀後半までは神に捧げる音楽(宗教曲)やオペラの伴奏として支えていた管弦楽団(オーケストラ)に光があたり、クラシック音楽の中心的存在でした。
交響曲を生み、発展させたのはハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンといわれています。
なかでもハイドンは「交響曲の父」と呼ばれ、交響曲の基本を作った作曲家で、作曲した交響曲は100曲以上という圧倒的に多い作曲数です。
また、モーツァルトは36歳の生涯でしたが、約40曲の交響曲を作曲し、ハイドンが生んだ交響曲ジャンルの発展に大きく貢献しました。
交響曲の作品番号の意味は?
交響曲は作曲家が楽曲を区別し、識別するために、作品番号を付けます。
基本的には作曲順に数字を付けますが、出版社によって番号が振られる場合も少なくありません。
楽曲に番号を付けるのは19世紀頃に始まり、作品番号が付いた例としては、ベートーヴェン作曲「交響曲第9番二短調Op.125」が挙げられます。
Op.は「Opus」の略で、ラテン語で「作品」を意味し、ベートーヴェンの楽曲の中で125番目という意味です。
ベートーヴェンの楽曲には番号が付いてないものもありますが、作品番号が付いている楽曲だけで138曲作曲しています。
作品番号を付けると、作曲者の人生においてどのくらいの時期に作曲された楽曲なのかが一目でわかるでしょう。
〜交響曲の歴史をさかのぼろう〜交響曲ができるまで

交響曲ができるまでの音楽の歴史は、紀元前14世紀にさかのぼります。
ここでは交響曲ができるまでの音楽の歴史を3つに分けて解説します。
- ルネサンス期
- バロック期
- 古典派期
交響曲ができるまでの音楽の歴史を知ると、どのような流れで交響曲が生まれたのかがわかり、より興味が湧くでしょう。
ルネサンス期(紀元前14~17世紀)
ルネサンス期は、器楽音楽が発展した時代です。
交響曲の形式は誕生してないものの、楽器が改良されてヴィオラ・ダ・ガンバなどの独奏楽器が誕生しました。
バロック期(17~18世紀初頭)
バロック期はオペラや宗教音楽が繁栄した時代です。
管弦楽団(オーケストラ)の形成が進み、バロック末期には協奏曲の形式が確立されました。
古典派期(18~19世紀初頭)
古典派期では交響曲の形式が確立します。
ハイドンを始め、モーツァルトやベートーヴェンが多くの交響曲を作曲し、交響曲の形式を確立しました。
古典派期以降はさまざまな作曲家によって、感情的で壮大な交響曲が多く作曲され、交響曲はクラシック界の中心的ジャンルになり、現在に至ります。
交響曲の特徴5つ

交響曲には特徴が5つあります。
作曲家により多少異なりますが、一般的な特徴は以下のとおりです。
- 多くの楽器が使われる
- 複数の楽章で構成されている
- ソナタ形式の使用
- さまざまな感情を表現している
- 主題の変奏や対比
交響曲の特徴を理解すると、交響曲をより楽しみながら聴けるようになります。
特徴① 多くの楽器が使われる
交響曲は大規模な管弦楽団(オーケストラ)によって演奏され、多彩な楽器が使われます。
使われる楽器は大きく分けて以下4つです。
- 弦楽器
バイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバス - 木管楽器
フルート、クラリネット、オーボエ、ファゴット - 金管楽器
ホルン、トランペット、トロンボーン、チューバ - 打楽器
ティンパニ、スネアドラム、バスドラム、シンバルなど
多くの楽器により、多彩な音色やダイナミクスが表現されます。
特徴② 複数の楽章で構成されている
交響曲は「楽章」という複数の小さな部分から構成されます。
一般的な構成は以下4つの楽章です。
- 第1楽章
ソナタ形式 - 第2楽章
緩やかな楽章。ゆっくりとしたテンポで穏やかな旋律が特徴的 - 第3楽章
軽快でリズミカル - 第4楽章
フィナーレ。活気に満ちた曲調が多い
楽章ごとに特徴が異なり、楽曲全体の構造や表現を豊かにします。
特徴③ ソナタ形式の使用
交響曲の多くは第1楽章がソナタ形式です。
ソナタ形式は物語のような流れであり、3つのセクションから構成されています。
- 提示部
楽曲の主要なメロディやリズムが紹介される部分。物語でいうと、主人公が紹介される部分 - 展開部
提示部で紹介されたメロディやリズムが変化する部分。物語でいうと、主人公が困難に直面したり、新しい場所に行ったりする部分 - 再現部
最初に登場したメロディやリズムが再び現れる部分。物語でいうと、主人公が困難を乗り越え、物語が完結する部分
ソナタ形式は1つの物語になっており、起承転結がある形式です。
オススメ記事
ソナタって?ソナチネとは違うの?筆者が激推しの美しい名曲を10選紹介◎
今回の記事では、ピアノの曲に多いソナタやソナチネの違いや形式、さらに「ピアノ ソナタ」、「ピアノが上達する練習曲を知りたいな」、「たくさん練習曲があるけど進める順番は?」の疑問にお答えしていきます。

特徴④ さまざまな感情を表現している
交響曲では、さまざまな感情や気持ちが表現されます。
多くの交響曲は劇的な展開や情熱的な表現を特徴としていて、作曲家は管弦打楽器の力強い響きを活かし、旋律やダイナミクスを表現します。
特徴⑤ 主題の変奏や対比
交響曲は楽曲の中で同じメロディ(主題)が少しずつ変わったり、対比したりするのが特徴的です。
例としては、交響曲の最初に美しいメロディが演奏されたとします。次にメロディが再び現れるときには少しテンポが速くなったり、演奏する楽器の組み合わせが変わったりします。
また、同じメロディが再度流れたとしても、最初とは異なる雰囲気で対比されることもあります。
交響曲と協奏曲の違いは?

交響曲は管弦楽団(オーケストラ)全体で演奏される楽曲で、協奏曲は管弦楽団(オーケストラ)と1人のソリストとの対話のようなかたちで演奏される楽曲です。
ここでは交響曲と協奏曲の違いを表にまとめています。
交響曲と協奏曲の違いを知ると、音楽の構造や表現方法について理解でき、音楽鑑賞の楽しみが深まるようになるでしょう。
| 交響曲 | 協奏曲 | |
|---|---|---|
| 演奏形態 | オーケストラ 全体で演奏 |
ソリストと オーケストラで演奏 |
| 演奏の主役 | オーケストラ | ソリスト (ピアノやヴァイオリンなど) |
| 楽曲構成 | 通常1~4楽章で構成 | 通常は1~3楽章で構成 |
| 楽章の特徴 | 各楽章で異なるメロディや リズムが楽しめる 第1楽章でソナタ形式を 使用することが多い |
ソリストとオーケストラが 対話するような演奏 カデンツァなど、ソリストとの 音楽的な対話を含むことがある |
| 主な楽曲 | ・交響曲第9番 (ベートーヴェン) ・交響曲第9番「新世界より」 (ドヴォルザーク) |
・ピアノ協奏曲第1番 (ショパン) ・ヴァイオリン協奏曲ニ長調 (チャイコフスキー) |
有名な作曲家と交響曲をご紹介◎

交響曲には多くの有名な楽曲があります。
ここでは作曲家を5人紹介し、有名な交響曲を10曲解説します。
有名な交響曲と作曲家を知ると、音楽鑑賞がより楽しめるでしょう。
ハイドン
ハイドンはオーストリア出身で、交響曲を生み、クラシック音楽に革新をもたらした作曲家です。
ハイドンの交響曲の特徴は以下の3つです。
- 多様な形式や構造(三部形式や独創的な楽曲構造)
- 対比と独創性(メロディとリズムの予想外の変化など多くの驚きを含む)
- 豊かな表現力(喜びや悲しみ、驚きなどの感情を表現)
ハイドンの交響曲は、古典派以降の音楽の先駆けとなるような要素がみられます。
交響曲第94番ニ長調「驚愕」
ハイドンが作曲した交響曲の中で、最も有名な楽曲です。
第2楽章で予期せぬ大きな音が入り「驚愕」させます。
ハイドンの幅広い表現力や独創性を示した作品です。
交響曲第45番ヘ短調「告別」
ハイドンがオーストリアのエステルハージ家で宮廷楽団長を務めていたときに作曲されました。
最終楽章にて演奏者が1人ずつステージを離れ、最後に2人だけが残り、照明が落とされる演出が特徴的です。
オススメ記事
”交響曲の父” ハイドン|有名曲10選を解説◎時代背景もご紹介!
交響曲の父といわれるハイドンをご存じですか?実はハイドンは、モーツァルトやベートーヴェンにも影響をあたえた偉大な作曲家なんです。 今回は、ハイドンの生涯や有名曲10選とその時代背景について解説していきます。

モーツァルト
モーツァルトはオーストリア出身で、古典派音楽の巨匠として知られています。
モーツァルトの交響曲の特徴は以下の3つです。
- メロディの美しさ(美しいメロディと旋律)
- 巧みな技術(バランスの取れた音楽の構造)
- 新しいアプローチ(古典派音楽の伝統を受け継ぎつつ、交響曲の形式や構造に新しい要素)
モーツァルトの交響曲は美しいメロディや巧みな技術により、多くの人に愛されています。
交響曲第40番ヘ短調
モーツァルトが作曲した交響曲の中で、最も有名な楽曲です。
第1楽章の力強い旋律や第4楽章の情熱的な終わり方が人々を魅了します。
交響曲第41番ハ長調「ジュピター」
モーツァルトが作曲した最後の交響曲の1つです。
壮大な雰囲気と複雑な構造により、モーツァルトの最高傑作ともいわれています。
ベートーヴェン
ベートーヴェンはドイツの作曲家で、古典派音楽からロマン派音楽への移行期において、最も重要な人物の1人です。
ベートーヴェンの交響曲の特徴は以下の3つです。
- 情熱と力強さ
- 革新性と独創性(古典派音楽の枠を超えて、新しい表現方法やアイデア)
- 楽器の可能性を最大限に引き出した曲調
ベートーヴェンの交響曲は楽器の可能性を最大限に活かし、情熱的な曲調が心をつかみます。
交響曲第5番ハ短調「運命」
ベートーヴェンが作曲した交響曲の中で最も有名な楽曲です。
力強く、壮大なスケールが特徴的です。
印象的な「ジャジャジャジャーン」の部分は諸説ありますが「運命がドアを叩く音」として、独特な緊張感を生み出します。
交響曲第9番ニ短調「合唱」
ベートーヴェンが作曲した最後の交響曲です。
「歓喜の歌」で知られるシラーの詩を元にした合唱楽章が含まれています。
交響曲の歴史において、管弦楽のなかに合唱が入ったのは革新的なアイデアであり、全体で100人以上の大規模な演奏は現在でも人々を圧巻させます。
オススメ記事
【ベートーベン 交響曲一覧表】1曲ずつ楽曲解説・作曲背景も合わせてご紹介◎
ベートーベンというと、第九や「運命」、のだめカンタービレで有名になった7番の他にも多くの名曲があります。今回は、ベートーベンの交響曲をすべて解説、交響曲の中で名盤とされている曲を取り出してみました。

ドヴォルザーク
ドヴォルザークはチェコの作曲家であり、ロマン派音楽の代表的な作曲家の1人です。
ドヴォルザークの交響曲の特徴は以下の3つです。
- 民族的な要素(民族音楽の旋律やリズム)
- 管弦楽の豊かな音色(管弦楽の楽器を効果的に使用)
- 情熱的な表現
ドヴォルザークの交響曲は民族的な要素を取り入れつつ、楽器を効果的に使用しています。
交響曲第9番ホ短調Op.95「新世界より」
ドヴォルザークの代表作の1つで、世界中で人気がある交響曲です。
新世界はアメリカを指しており、ブラックミュージック特有の音階やリズムを導入しています。
特に第2楽章の美しいメロディと感情表現は多くの人を魅了し、日本では歌詞を付けられ「家路」のタイトルで愛されています。
交響曲第7番ニ短調Op.70
交響曲第7番ニ短調Op.70は、劇的な展開が特徴的です。
特に第1楽章のダイナミックな展開に、引き込まれます。
スラブ音楽(民族音楽)を感じさせるような箇所も存在し、ドヴォルザークの魅力が詰まった交響曲といえるでしょう。
チャイコフスキー
チャイコフスキーはロシア出身で、ロマン派時代の作曲家です。
チャイコフスキーの交響曲の特徴は以下の3つです。
- メロディの美しさ(繊細で感動的なメロディ)
- ロシアの民族的な要素(ロシア民謡や舞曲の要素)
- 緻密な技術(複雑な楽曲構造)
チャイコフスキーの交響曲は美しいメロディや民族的な要素により、一風変わった交響曲として人気があります。
交響曲第4番ヘ短調Op.36
ファンファーレのような雰囲気で惹きつけられた後、ロシア民謡や舞曲のような雰囲気が続きます。
第4楽章のスピード感をもちつつ、情熱的にフィナーレを迎えるのは圧巻です。
交響曲第6番ヘ短調Op.74「悲愴」
交響曲第6番ヘ短調Op.74「悲愴」はチャイコフスキーが作曲した最後の交響曲です。
各楽章で悲しみや情熱、美しさなどが入り交じり、感動を呼びます。
オススメ記事
【チャイコフスキーの名曲10選】生涯を年表で解説!ぷちエピソードも◎
チャイコフスキーの名曲は?生涯についても解説します!順風満帆な音楽人生を送ったのだと思いきや、実は苦労が絶えない作曲家でした。筆者おすすめの隠れた名曲もご紹介しますので、最後までご覧いただけると嬉しいです。

まとめ

この記事では交響曲とは何か、協奏曲との違いについて解説してきました。
- 交響曲とは?
複数の楽章からなる大規模な作品で、管弦楽団(オーケストラ)によって演奏される楽曲ジャンルです。 - 交響曲と協奏曲との違い
| 交響曲 | 協奏曲 | |
|---|---|---|
| 演奏形態 | オーケストラ 全体で演奏 |
ソリストと オーケストラで演奏 |
| 演奏の主役 | オーケストラ | ソリスト (ピアノやヴァイオリンなど) |
| 楽曲構成 | 通常1~4楽章で構成 | 通常は1~3楽章で構成 |
| 楽章の特徴 | 各楽章で異なるメロディや リズムが楽しめる 第1楽章でソナタ形式を 使用することが多い |
ソリストとオーケストラが 対話するような演奏 カデンツァなど、ソリストとの 音楽的な対話を含むことがある |
| 主な楽曲 | ・交響曲第9番 (ベートーヴェン) ・交響曲第9番「新世界より」 (ドヴォルザーク) |
・ピアノ協奏曲第1番 (ショパン) ・ヴァイオリン協奏曲ニ長調 (チャイコフスキー) |
交響曲について理解して、音楽鑑賞を楽しみましょう!
オススメ記事
【ベートーベン 交響曲一覧表】1曲ずつ楽曲解説・作曲背景も合わせてご紹介◎
ベートーベンというと、第九や「運命」、のだめカンタービレで有名になった7番の他にも多くの名曲があります。今回は、ベートーベンの交響曲をすべて解説、交響曲の中で名盤とされている曲を取り出してみました。

オススメ記事
”交響曲の父” ハイドン|有名曲10選を解説◎時代背景もご紹介!
交響曲の父といわれるハイドンをご存じですか?実はハイドンは、モーツァルトやベートーヴェンにも影響をあたえた偉大な作曲家なんです。 今回は、ハイドンの生涯や有名曲10選とその時代背景について解説していきます。