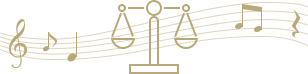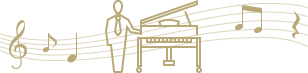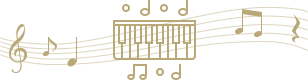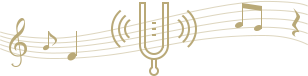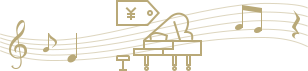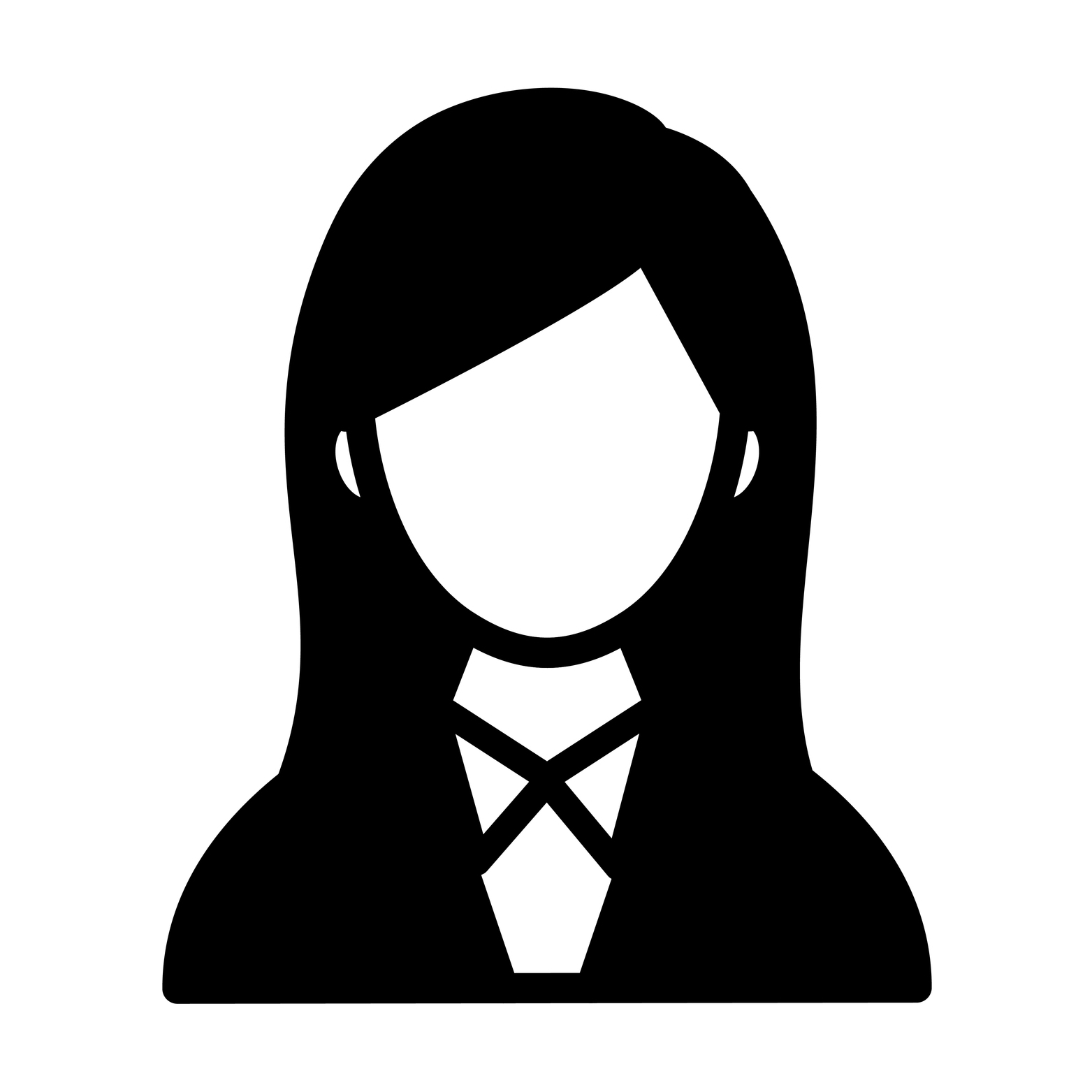
ピアノ歴20年以上のWEBライターです。コンクールや受験、さらにピアノ指導経験を活かした記事作成を行っています。
目次
ピアノ教本の『バーナムピアノテクニック』には全7巻のシリーズがあり、ピアノを習い始めた生徒さんが最初に使う練習曲集としても知られています。
子どもはもちろん、大人のピアノ初心者にも最適な『バーナムピアノテクニック』の最大の魅力は、シンプルな練習曲と親しみやすさです。
ピアノ経験者の多くが支持するバーナムですが、全シリーズを習得すべきか、各教本の難易度がどのくらいなのか疑問に感じますよね。
そこで今回の記事では、『バーナムピアノテクニック』を学ぶ順番や難易度、さらに効果的な練習方法についてご紹介していきます。
バーナムピアノテクニックとは?

『バーナムピアノテクニック』の著者は、アメリカのピアノ教育において多大な功績を残した作曲家エドナ・ベイ・バーナムです。
日本でも著者の名前を使用した『バーナムピアノテクニック』というタイトルがつけられ、多くのピアノ指導者や学習者から高評価を得ています。
『バーナムピアノテクニック』は、導入教材の「ミニブック」や「導入書」をはじめ、実践練習をメインとした「第1〜第4巻」、すべての調性のスケールや楽曲が学べる「全調の練習」まで全7巻です。
各教本に掲載される4〜8小節のシンプルな練習曲には、タイトルと棒人形のイラストが描かれています。例えば「歩こう」「スキップしよう」など。
これらのタイトルとイラストは、ピアノ演奏に必要なテクニックや表現力を学ぶための大きなヒントとなり、全シリーズに共通しています。
効果はあるの?
バーナムの練習曲はシンプルなので、本当に効果があるのか疑問に感じる方もいますよね。ピアノレッスンの頻度や年齢にもよりますが、効率よく練習を続けていくと効果はあります。
なぜなら『バーナムピアノテクニック』には、ピアノ演奏に必要な技術とともに表現力を養う要素が含まれているからです。
また、バーナムはブルグミュラーやツェルニーといった練習曲集にも繋がっていくので、上手く併用するとより効果が期待できます。
バーナムを練習するメリット&デメリット
『バーナムピアノテクニック』は多くのピアノ指導者が絶賛する教本ですが、使い方次第ではデメリットになってしまうこともあります。
ここでは『バーナムピアノテクニック』のメリット・デメリットを解説していきます。
バーナムピアノテクニックを使うメリット
『バーナムピアノテクニック』では、テクニックと同時にピアノを弾く時のタッチや脱力を学ぶことができます。
さらに、棒人形のイラストが音作りのヒントになり、早い段階でピアノ演奏に必要な表現力も身につくのです。
また、短い曲で演奏の完成度を上げることで、ピアノ練習のモチベーションもアップします。
『ハノン』のような訓練性が強い練習曲と異なり、どのような音で弾きたいかをイメージしながら練習する点が『バーナムピアノテクニック』のメリットと言えますね。
バーナムピアノテクニックのデメリット
『バーナムピアノテクニック』は各曲が短く弾きやすいため、練習目的がクリアできたか曖昧になってしまう点がデメリットと言えます。
自分のレベルに合ったバーナムからスタートしても良いので、サラッと弾かずにしっかりと掘り下げた練習が望ましいです。
【難易度つき】学ぶ順番は?

ここからは『バーナムピアノテクニック』を学ぶ順番を、難易度別にご紹介します。(あくまでも目安です。)
| 導入〜初級 |
|
| 初級 |
|
| 初級〜中級 |
|
導入〜初級
- 1. ミニブック
- 2. 導入書
- 3. 第1巻
最初に学ぶべき『バーナムピアノテクニック』は、初めてピアノに触れる日から使える「ミニブック」です。その後、「導入書」から「第1巻」に進みます。
この3冊の『バーナムピアノテクニック』は、ピアノの導入期から初級レベルの教本です。子ども向けのピアノ教本と思われがちですが、大人の初心者にも最適な内容となっています。
一方で、生徒さんの習得度によって「導入書」または「第1巻」から始めるケースも多いですね。
ちなみに、同レベルのピアノ教本として『バイエル』や『トンプソン』などの導入編が挙げられます。
初級
- 4. 第2巻
- 5. 第3巻
ピアノ初級レベルの「第2巻」と「第3巻」では、ハ長調以外の練習曲も増えてきます。臨時記号の読み方を「第1巻」で習得し、♯や♭を調号として理解する段階が「第2巻」と「第3巻」です。
この段階で『ハノン』や『ル・クーペ』を併用し、テクニックの応用力を身につけると演奏レベルの向上に繋がります。
さらに、『ブルグミュラー25の練習曲』を取り入れたり『ツェルニー』を代用するなど、生徒さんのレベルに合わせて選択肢の幅も広がります。
初級〜中級
- 6. 第4巻
- 7. 全調の練習
「第4巻」は、『バーナムピアノテクニック』の集大成と言える教本です。初級から中級にステップアップする段階で、『ツェルニー30番練習曲』や『モシュコフスキー20の小練習曲』といった教本との併用がおすすめ。
そして『全調の練習』には、24すべての調性を楽しく学ぶ工夫が散りばめられています。調号が多い楽曲でも親しめるので、子どもから大人まで使えるピアノ教本と言えます。
バーナムを1冊ずつ解説◎

ここでは、『バーナムピアノテクニック』全7巻を1冊ずつ詳しく解説していきます。全7巻に共通しているのは、各曲がグループ1〜5に分けられていることです。
各曲にはタイトルと棒人形のイラストが描かれ、テクニック習得のヒントになります。1冊にかかる期間には個人差がありますが、「ミニブック」や「導入書」は比較的早く習得できると思います。
バーナムピアノテクニック ミニブック
【対象年齢やレベル】幼児〜小学生または大人のピアノ初心者
「ミニブック」は、ピアノを始めてすぐに使える教本です。譜読みの知識がない状態でも「ミニブック」で学べるので、ピアノを習い始めて最初に触れる教本と言えます。
まずは、音符に書かれている指番号を理解して、メトロノームを使って音の長さを覚える練習から始めると良いです。
グループ1では、ドとレまたはドとシといった隣り合う音を中心とした練習曲が多いです。片手ずつレガートやスタッカートで弾いたり、両手で弾く練習が含まれます。
グループ2とグループ3は音の幅が広がり、音階の準備練習や和音も登場。さらにグループ4では、長調と短調のイメージを理解するための練習曲を学びます。
最後のグループ5には8分音符が出てきて、「走ろう」「ブランコ」といった曲を通して音符の長さを学びます。
バーナムピアノテクニック 導入書
【対象年齢やレベル】小学校低学年または大人のピアノ初心者
「導入書」は「ミニブック」よりも難しくなり、グループ1〜グループ3には8分音符や3連符、装飾音符も出てきます。ただし、すべてハ長調で書かれ黒鍵を使うことはありません。
グループ4とグループ5に入ると臨時記号がたくさん出てくるので、曲調の変化や長調と短調の違いについて理解を深めていきます。
臨時記号に苦手意識を持ってしまうと、ハ長調以外の曲でつまづきやすいです。そのため、「導入書」の段階できちんと臨時記号を学ぶことがレベルアップに繋がります。
楽譜で♯(シャープ)や♭(フラット)がついている音に印をつけたり、長調と短調の曲を色で表現するなど、練習方法を工夫してみましょう。
バーナムピアノテクニック1
【対象年齢やレベル】小学校低学年〜中学年またはピアノ歴1年未満
「第1巻」は、ピアノ導入期から初級にステップアップするための教本です。グループ1〜グループ5までハ長調で書かれていますが、臨時記号も出てきます。
また、スケールとアルペジオ、三和音の弾き方に加えて、ペダルの踏み方などピアノ演奏の基本テクニックの習得を目指す段階です。
グループ1の「歩こう、走ろう」には16分音符も登場します。そのため、指をすばやく動かす練習やメトロノームを使って音の長さを覚える練習が不可欠です。
そして、グループ5にはペダルを踏み変える練習やスタッカート奏法、さらに半音階の練習曲もあります。半音階を弾く時は指使いが重要なので、片手ずつ丁寧に練習することが大切です。
バーナムピアノテクニック2
【対象年齢とレベル】小学校中学年〜高学年またはピアノ歴1年以上
「第2巻」では、グループ1〜グループ3でスケールや連打の練習、グループ4とグループ5で左右のアルペジオと総合的なテクニックの習得を目指します。
さらに、ハ長調以外のト長調やヘ長調といった練習曲も登場。黒鍵を弾く時のタッチや指使いを学びながら、譜読みもレベルアップさせることが目的です。
指先の瞬発力を鍛える練習やアルペジオで親指をくぐらせる弾き方の習得など、ツェルニーやブルグミュラーに進むためのスキルを身につける段階と言えます。
難しいと感じる曲も増えるので、反復練習や片手ずつ弾く練習を取り入れて完成度を上げていきましょう。
オススメ記事
初心者必見|一日5分のスケール練習でピアノスキルを劇的に向上させる方法
スケール練習の進め方や1日5分の練習の効果についても紹介します!スケール練習の方法を知ると、指の力や音程感覚が鍛えられ、ピアノが上達します。

バーナムピアノテクニック3
【対象年齢とレベル】小学校高学年〜中学生またはピアノ歴2年以上
「第3巻」はピアノの基礎固めと言える内容で、グループ1〜5までの基本テクニックの総合的な練習曲を通して、より高度な技術の習得を目指すための教本です。
オクターブや3度または6度の重音奏法、左右交互に弾くアルペジオなど、ピアノ初級でありながら難しい曲が増えていきます。
重音奏法では、指をしっかり上げて音が残らないように丁寧に練習しましょう。楽譜通りの指使いを守って、正しいテンポで弾くことが大切なのです。
オススメ記事
【経験者が語る】ピアノのアルペジオのコツをご紹介!パターンも丁寧に解説します!
ピアノのアルペジオを弾くコツやパターンに加えて、おすすめの楽曲と練習方法もご紹介します。アルペジオは、演奏を華やかにする効果もあり、幅広いジャンルのピアノ音楽に使われています。スムーズに弾けるようになるとレパートリーも広がり、ピアノのテクニックが上達するのでぜひ練習してみましょう!

バーナムピアノテクニック4
【対象年齢とレベル】中学生〜高校生またはピアノ歴3年以上
「第4巻」は、『バーナムピアノテクニック』の総まとめです。
スケール・アルペジオ・オクターブ・スタッカート・重音奏法・ペダル・トリルといったテクニックを総合的に学びます。
また、「かけ足で階段を上がっておりよう」や「バスケットボールの練習」など、音域が広い曲も多いです。これらは、腕の使い方や正しい手のポジションを覚え、効果的なペダリングの習得を目的とした練習曲と言えます。
「第4巻」でもメトロノームに合わせて弾く練習や指先の瞬発力を鍛える訓練など、それぞれの曲に最適な練習方法を試していきましょう。
バーナムピアノテクニック 全調の練習
【対象年齢とレベル】初級から中級レベルのピアノ学習者
「全調の練習」は、『バーナムピアノテクニック』の番外編に位置づけられる教本です。練習曲にはすべての調性が使われ、音階練習の強化にも繋がります。
8〜16小節の練習曲にはタイトルとイラストが描かれ、長調と短調の違いを学びながら譜読みのトレーニングもできます。
さらに、短調は「和声短音階」と「旋律的短音階」が記載されているので、ハノンの代用としてもおすすめです。
バーナムの効果的な使い方◎

『バーナムピアノテクニック』は基本練習が主体となっているので、応用的な教本を併用するとより効果的です。
例えば、初級から中級レベルの入口と言える「第4巻」と『ブルグミュラー25の練習曲』を併用すると、テクニックと表現力を同時に強化できます。
ブルグミュラーもタイトルからインスピレーションを得て、音楽的に弾くことが求められる練習曲ですね。簡潔にまとめられたバーナムと実践的なブルグミュラーの併用で、より完成度の高い演奏を目指せます。
一方で、テクニックを重視したい時は『ツェルニー30番』との併用がおすすめです。バーナムとツェルニーの共通するテクニックを強化すると、応用練習にもスムーズに取り組めると思いますよ。
さらに『バーナムピアノテクニック』には、最高難度のショパンやリストの練習曲のヒントとなる要素も含みます。そのため、上級レベルのピアノ曲を練習しながらバーナムを有効活用する方法も効果的です。
まとめ

今回は、『バーナムピアノテクニック』について詳しく解説してきました。
音大生やピアノ教師も絶賛する『バーナムピアノテクニック』には、ピアノ練習が楽しくなる工夫がたくさんあります。さらに、大人になってピアノを習う方にも使いやすいと好評です。
ピアノ練習でつまづいた時にも役立つ『バーナムピアノテクニック』、ぜひお試しください。
オススメ記事
【初心者必見】ピアノ練習曲|進める順番は?ピアノ経験者が語る有名曲と教本◎
ピアノが上手になりたい方へ。ピアノの練習曲を進める順番を解説します。初心者向けの練習曲から、上級者向けの曲まで、難易度別に9つの教本を紹介します。ピアノの教本や練習曲を進める順番がわかることで、ピアノが上達する道筋が見えるようになります。弾きやすい楽譜を自分で見分けるポイントも解説しています。